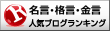この7つが私たちを破壊する。
労働なき富。
良心なき快楽。
人格なき学識。
献身なき宗教。
理念なき政治。
人間性なき科学。
道徳なきビジネス。
byマハトマ・ガンディー
ガンディーはインド独立運動の指導者で長きにわたるイギリス支配からの独立に大きな貢献をし、「インド独立の父」と呼ばれています。
ガンディーはイギリス領インド帝国の大臣の子として生まれ、いわゆる貧困層の出身ではなく、言うなれば土着のインド人ではありながらもエリート家庭で育ちました。
子どもの頃は素行が良くなかった逸話なども残されていますが、18歳で宗主国であるイギリスへ弁護士となるべく法律を学ぶために留学し、卒業後にイギリス領南アフリカ連邦にて弁護士として働くのですが、そこで待っていたのは目を覆いたくなるような現実でした。
それは、イギリス人によるインド人への過度な人種差別です。
インド人であるというだけの理由で、全く理解できない数々の差別を目にました。
ガンディーの独立運動で有名なのは、非暴力による非服従ですので、おそらく数々の暴力も目にされたのだと思います。
ここでガンディーはこのままではいけない、 到底納得できないと考え、インド独立を志すようになります。
よく独立、独立とは言うものの、独立とはあくまで手段であり、この場合のインド独立の目的は過度な人種差別から同胞を守る為だったのだと思います。
ガンディーはその後、非暴力の非服従による独立運動を推進し、このガンディーの考えに多くの国民が共鳴しました。
ガンディーで有名な写真は白い生地を身にまとい糸車を回している写真です。
これはイギリス製品の不買運動で自国の綿花から服を作った為です。
この当時、インドは綿花の主要産地でしたが、綿花は全てイギリスへ輸出し、イギリスで糸になり、生地になり、そして衣服になった後にインドへ再度入ってくるという有様で、写真からも分かる通り、インドに綿花はあっても糸や生地を生産する技術が無かったことが分かりますね。
ガンディーの非暴力による非服従での独立運動に対する姿勢が感じられますよね。
有名な塩の行進も、元を辿れば自国で塩を、という精神からきているものです。
ガンディーはあくまで非暴力による独立を貫きました。
独立と言えば多くの国は武力行使で成しえましたので、インドの独立はそれぐらい特殊な形だったと言えます。
結果的にインドは独立を果たすのですが、ガンディーは国交問題の為に自分の信ずる宗教とは異なるイスラム教へも理解を示し、ヒンドゥー教徒とイスラム教徒で何とか互いに歩み寄れないかと考え、何度も断食を繰り返し訴えますが、過激なヒンドゥー教徒により、「イスラム教徒へ譲歩しすぎだ、あなたはヒンドゥ―教徒の敵だ」とされ、同じ宗教を信ずるヒンドゥー教徒に暗殺をされて、その生涯を終えることになりました。
長くなってしまいましたが、本日はそんなガンディーの言葉です。
人とはどうあるべきかを説いた言葉です。
全てにおいて最もだと言えることではあります。
例えば「良心なき快楽」は人が追い求める欲求はすべて良心ありきの事でなくてはならないということかと思います。
快楽は様々ですが、人を騙して得る快楽や人を貶めて得る快楽ではダメだということですね。
「人格なき学識」については、一見、学識と人格は関係のない事柄に感じられますが、これはまさに自分の言っていることが正論であれば問題ないとし、相手をやりこめる愚を説いていると思います、学識をひけらかすのも同じ愚ですよね。
学識は人格あって初めて有用になるものなのではないでしょうか。
「献身なき宗教」や「理念なき政治」については、どちらも一番大切な元が無いと言っていると思います。
献身があって初めてそれは宗教、ついては自分の信じるものだと言え、理念があって初めて政治も成り立つのだと思います。
「道徳なきビジネス」は、仕事をしている私自身も常々考えることです。
相手のことを考えないビジネスはビジネスではなく、単なる金儲けであり、卑しい行いです。
損得勘定が働く行いこそ、人ありき、人の気持ちありきで、道徳にかなった考えや行動が大切だというのは、今の金儲け第一のビジネス社会に響く言葉だと思います。
ブログランキングに登録してます。
応援宜しくお願いします。