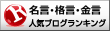:部下:
これはひどい。
戦に勝ったのにその財をすべて戦費に当てたり部下に与えたり。
獅子王(ししおう…アレキサンダーのこと)、あなたは自分のために何を残すおつもりですか!?
:アレキサンダー:
希望を残せばそれでよい。
byアレキサンダー(アレクサンドロス大王)…映画「アレキサンダー」より
上記の言葉は実際のアレキサンダーの言葉ではなく、映画からの引用です。
この言葉が映画「アレキサンダー」の中で一番心に残っています。
映画自体は世間的に良い評価ではなかったみたいですが、私は好きでした。
ミーハーな部分として戦闘シーンがかっこいいのと、アレキサンダーが辿った歴史、そして最期を迎えるまでのストーリーも良かったです。
アレキサンダーっていったい何をした人なのかざっくりと説明したいと思います。
アレキサンダーはギリシアの北部であるマケドニアにという辺境の地にて生まれました。
父は名君と言われたフィリッポス2世です。
このフィリッポス2世はアレキサンダーが20歳のときに暗殺され、アレキサンダーがそのまま王位に就きます。
アレキサンダーは王位継承で揺れるマケドニアをまとめ、ギリシアの都市国家たちと戦い、同盟を結び支配下に置くことに成功しました。
ギリシアをまとめた後、悲願であるペルシアへの侵攻に舵を切ります。
そして強大であった当時のペルシア帝国を何度も打ち破り領土を拡大していきました。
アレキサンダーは溢れんばかりの野心と天才的な軍事センスにより連戦連勝で領土を広げていき、民衆も付き従う兵士もアレキサンダー万歳という雰囲気になっていくのですが、アレキサンダーの野心はどれだけ領土が広がっても尽きることはなく、戦争に次ぐ戦争をどんどん仕掛けていきます。
そして、徐々に民や兵士もアレキサンダーの野心に付き合いきれなくなり、心が離れていきます。
兵士とすれば勝って戦が終わるどころか勝ってもまた次の戦に駆り出されるだけです。
故郷からも遠く離れ、もう帰るのだっていつになるかわかりませんし、そもそも当時の時代背景を考えれば、戦うのはもちろん命懸けですが、帰るのも命懸けです。
勝って故郷から離れ、また勝って更に故郷から離れていくのですから、兵士としては耐えられないのも分かりますよね。
アレキサンダーは戦闘の際も王様らしく後ろでどっしりと構えるのではなく、自ら先頭にたって敵兵へ突っ込んでいくタイプだったようです。
部隊の士気を上げるために将自ら前線で戦うというのは良く聞く話ですが、アレキサンダーの場合は、単純に戦が好きで前線で戦いたいタイプだったのかもしれません。
戦で勝つのが好きだった為、将自らの突撃は兵の士気を上げると察知し、理性的に動いていたのかもしれませんが、理性があれば、領土を広げていく中で部下の士気低下に気付き、対策を講じたはずです。
結局アレキサンダーは部下の反発に遭い、引き返すことを決め、バビロンという街まで戻ってきます。
そしてアレキサンダーはそのバビロンの地にて亡くなります。
早過ぎる死でした、まだ32歳の若さだったそうです、王位継承から12年でした。
この12年の間に帝国をどんどん広げていき、急に亡くなる、まさに風のように現れ、風のように去っていったのでした。
アレキサンダーの死因には諸説があり、伝染病説や暗殺説などが有名です。
今となっては真意はわかりませんが、暗殺だとしたら、理由はやはり周囲が付いていけなかったからだと思われます。
アレキサンダーは戦が好きだったと思われる為、王ではなく軍師という立場でしたらまた結果は変わってきたかもしれません。
しかし、軍師であっても王の了承なしに戦争は仕掛けられないでしょうから、アレキサンダーが一介の軍師であれば、ここまで領土を広げられなかったかもしれません。
本日はアレキサンダーの言葉とともにアレキサンダーの生涯を簡単にご説明しました。
アレキサンダーなんて遠い昔の遠い国の話だと思うでしょうが、今私たちが使う日々の言葉にもアレキサンダーが語源に強く結びついているものがあります。
それはご飯を食べ終わったときに言う「ごちそうさま」です。
ごちそうさまは、漢字に直すと「御馳走様」です。
この「御馳走様」から丁寧な気持ちを表す「御」と敬う気持ちの「様」を取りますと、「馳走」になります。
この「馳走」、見た通りの意味です、走り回る?駆け回る?…なぜご飯を食べ終わった後に走り回るのか?と思いませんか。
これは、韋駄天(いだてん)と呼ばれる神が、仏陀(ブッダ)の為の食材を方々を走り回って集めてきたことに由来すると言われています。
韋駄天は走るのが早いことで有名な神なので、走り回って食材を集めるというのもイメージしやすいかもしれませんね。
ここで馳走の由来が韋駄天が走ったからだということはご理解いただけたはずです。
そして、この韋駄天の由来がアレキサンダーなのです。
この韋駄天は仏教の神なのですが、元々はヒンドゥー教の神のスカンダ―からきているそうです。
アレキサンダーはアラビア語でイスカンダルと言いますので、そこがスカンダ―の語源ではないかと言われてるそうです(諸説あり)。
いかがでしたでしょうか。
日々何気なく使っている「ごちそうさま」がアレキサンダーに結びつくなんて思わないですよね。
アレキサンダーがインドまで遠征をしたからこそヒンドゥー教の神様の名前に使われたのでしょうから、アレキサンダーがいなかったら、アレキサンダーじゃない人が東方遠征をしていたら、「ごちそうさま」ではなくて違う言葉を使っていたのかもしれませんよね。
こういった言葉の背景を探ってみて意外な人物が由来になっていることに気付くと、改めて歴史の壮大さに驚かされますよね。
アキレス腱ってあのアキレスからきていたのかというのは小学生や中学生の頃に驚くあるあるネタですよね。
ブログランキングに登録してます。
応援宜しくお願いします。